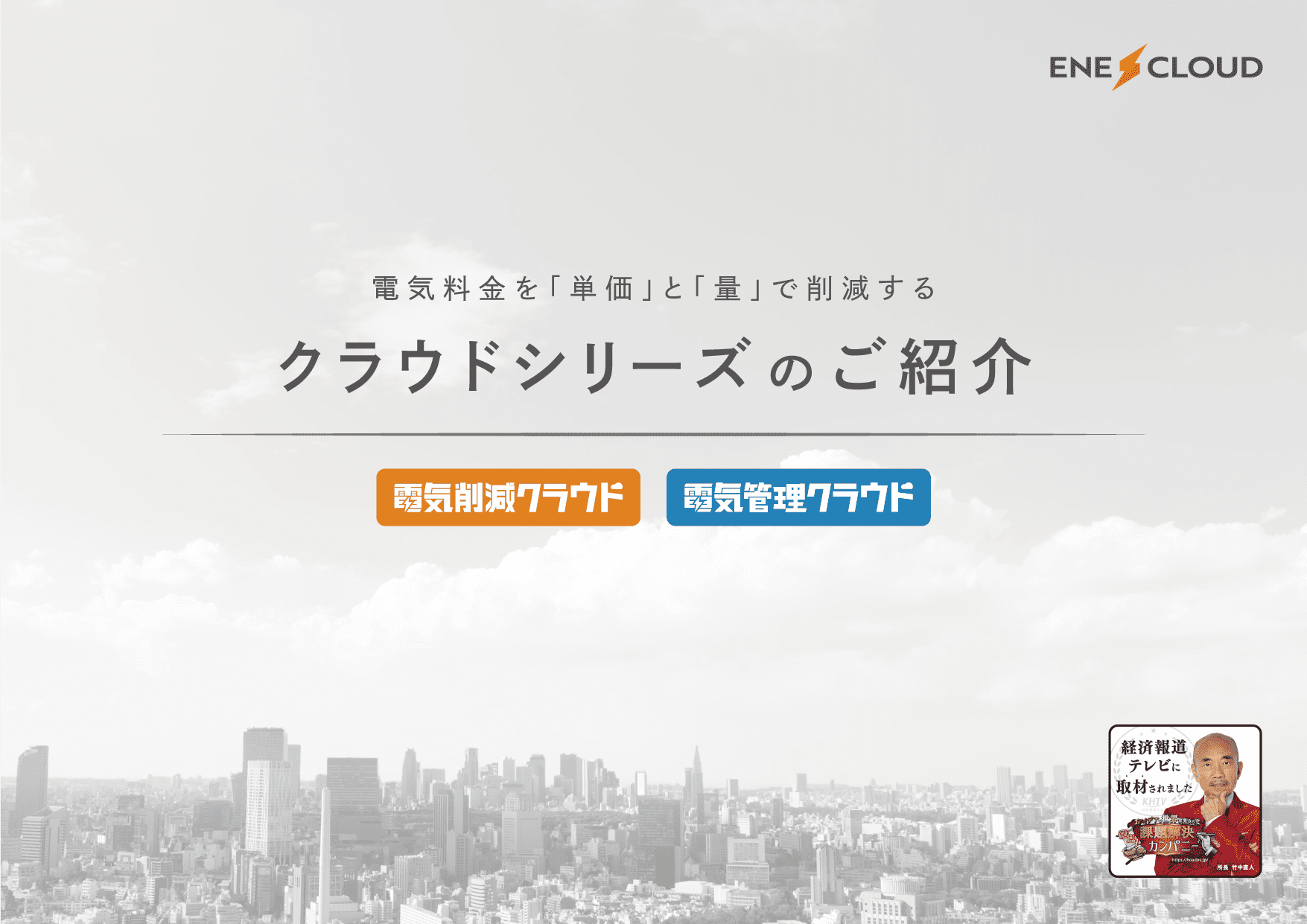容量市場が新電力に与える影響とは?中小企業による新電力選びのポイントも解説
2024年、容量市場の本格運用が始まり、新電力の経営環境に大きな変化が生じています。
一部の小売電気事業者では、この制度に伴って発生する「容量拠出金」の負担が増加し、そのコストを電気料金に転嫁する動きも見られます。
この影響は、新電力と契約している中小企業を含む需要家にとって、電気料金の上昇や契約先の撤退リスクなど、見過ごせない問題となりつつあります。
本記事では、容量市場と容量拠出金の基本的な仕組みをはじめ、新電力に与える具体的な影響、そして今後の電力契約で失敗しないための「新電力選びのチェックポイント」をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.容量市場とは
- 1.1.容量拠出金とは
- 2.容量拠出金が新電力に与える影響
- 2.1.電気料金に影響が及ぶ可能性も
- 3.容量市場を踏まえた新電力選びのチェックポイント
- 3.1.経営は安定しているか
- 3.2.自社で発電設備を保有しているか
- 3.3.資本力はあるか
- 3.4.電気料金の内訳を公開しているか
- 4.まとめ
容量市場とは
容量市場が新電力に与える影響を知るには、容量市場と容量拠出金について理解を深めることが重要です。
容量市場とは、4年後に必要となる電気の供給力をオークション形式で取引する市場のことです。簡単にいうと、発電事業者の供給力を価値に変えて、国内における将来の電気供給力を確保する仕組みを指します。
容量市場により、発電事業者は電気の供給力を約束する対価として、安定した収益を得られるようになります。発電設備のメンテナンスや新設が容易になるため、電力の安定的な供給を維持することが可能です。これにより、需給バランスの乱れによる大規模な停電や、供給電気の減少による電気料金の高騰が防止されるため、法人を含む需要家にとっても好ましい効果が期待できます。
容量拠出金とは
容量拠出金とは、“将来必要となる電気の供給力を確保できる対価”として、小売電気事業者や一般送配電事業者、配電事業者がOCCTOに対して支払う費用です。容量市場において、OCCTOは供給力を約束する発電事業所に対し「容量確保契約金額」を交付することから、容量拠出金は容量確保契約金額の原資といえます。
日本では、2020年に容量市場が開設され、同年7月に対象実需給年度を2024年としたオークションが開催されました。そのため、2024年から小売電気事業者に対して容量拠出金の支払義務が生じています。
容量拠出金が新電力に与える影響
新電力とは、2016年の「電力の小売全面自由化」以降に電力業界に新規参入した小売電気事業者のことです。基本的には旧一般電気事業者以外の事業者を指します。
容量市場は、新電力の経営に大きな影響を与えています。具体的には、容量拠出金の負担によって新電力の経営が圧迫されています。
上述のとおり、新電力は電力の小売全面自由化をきっかけに登場した事業者であることから、旧一般電気事業者に比べて経営基盤が弱く、資金力が低い傾向にあります。また、旧一般電気事業者は大規模な発電設備を持っていることが多く、その場合は容量確保契約金額を受け取れます。一方で、新電力は発電設備を持っていないことがほとんどのため、容量確保契約金額の受け取りがなく、容量拠出金を負担するだけです。
こうした背景から、多くの新電力で支出が大幅に増えてしまい、それが経営を圧迫する要因となっています。
電気料金に影響が及ぶ可能性も
容量拠出金は、本来なら小売電気事業者が負担する費用です。しかし、多くの新電力では需要家の電気料金に転嫁しているのが現状です。そのため、電気料金が値上がりします。
もちろん、なかには経費削減や経営体制の見直しなどの企業努力により、容量拠出金の負担を自社だけでまかなっている新電力もあります。
しかし、2024年から容量拠出金の負担が小売電気事業者の義務となったため、今後需要家の電気料金に転嫁される可能性は十分にあると考えられます。また、容量拠出金を自社でまかなった結果、経営不振により事業からの撤退や倒産・廃業に追い込まれる場合もあり、そうなると現在の電気契約を継続できなくなる可能性もあります。
容量市場を踏まえた新電力選びのチェックポイント
契約している新電力が、容量市場の影響で倒産・廃業する可能性はゼロではありません。仮にそうなった場合は、電気の供給停止日までに別の新電力(小売電気事業者)と契約を結ぶ必要があります。
こうした手間を省くためには、容量市場の影響を受けつつも安定して電気を供給し続けられる新電力と契約を結ぶことが重要です。
以下でご紹介する新電力選びのチェックポイントをぜひ参考にしてみてください。
経営は安定しているか
新電力を選ぶ際は、経営が安定しているかどうかを確認することが重要です。
例えば、販売実績が豊富だったり、グループ会社が旧一般電気事業者だったりする場合は、電力業界のノウハウを活かした経営ができていると判断できるため、安心して利用できます。
自社で発電設備を保有しているか
繰り返しになりますが、自社で発電設備を持っている新電力は、容量拠出金を支払うと同時に、容量確保契約金額を受け取ります。そのため、容量市場による影響が小さく、容量拠出金が需要家の電気料金に転嫁されることもなければ、経営不振に陥る心配も少ないといえます。
一方で発電設備を持っていない新電力は、容量確保契約金額は受け取れないものの、容量拠出金の支払義務は生じます。つまり、容量市場による影響が大きく、最悪の場合は事業からの撤退や倒産・廃業に追い込まれる可能性があります。
こうした背景から、新しく契約を結ぶ新電力には、自社で発電設備を保有している会社を選ぶことが重要です。
資本力はあるか
電力業界では今後もさまざまな制度や仕組みが導入される可能性があります。容量市場のように、小売電気事業者の負担が増える見直しが行われることも十分に考えられるため、新電力を選ぶ際は資本力もチェックすることが重要です。
例えば「電気事業のほかにもさまざまな事業を行っている」「大企業の子会社である」といった特徴を持つ新電力なら安定した資本力が期待できるため、安心して電気契約を結べます。
電気料金の内訳を公開しているか
新電力を選ぶ際は、料金プランの分かりやすさにも目を向けることが重要です。特に電気料金の内訳は新電力選びの検討材料になるため、公開されているか否かをよく確認することをおすすめします。
あわせて、容量拠出金や燃料費等調整額の扱い、料金変動のリスクを公開しているかどうかも確認しておくと安心です。もし公開されていない場合は、知らぬ間に電気料金が値上がりする可能性があるため、利用を避けることをおすすめします。
まとめ
この記事では、容量市場が新電力に与える影響について以下の内容を解説しました。
- 容量市場は、新電力の経営を圧迫する要因になっている
- 新電力のなかには、事業が成り立たないことを理由に、容量拠出金を需要家の電気料金に転嫁している会社もある
- 法人を含む需要家は、容量市場の影響を受けつつも安定して電気を供給し続けられる新電力と契約を結ぶことが重要
- 新電力選びでは「経営は安定しているか」「自社で発電設備を保有しているか」「資本力はあるか」「電気料金の内訳を公開しているか」をチェックするのがおすすめ
容量市場は新電力の経営に影響を与え、ひいては需要家の電気料金の値上がりにつながります。
とはいえ、新電力には独自の料金プランが豊富に用意されています。より自社に合った電気契約が可能なため、新電力との契約にこだわりたい場合もあるかもしれません。新電力を利用する際は、容量市場の影響を受けつつも安定して電気を供給し続けられるかどうかを軸に会社・料金プランを選ぶことが重要です。
エネクラウド株式会社の『電気削減クラウド』なら、複雑な電気契約の最適化を、専任担当者のサポートを受けながら効率的に進めることができます。メリットやサービス内容については資料で詳しく解説しているため、この機会にぜひご覧ください。
『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。